HTMLの記述とブラウザ
最近ではMocrosoft社のWordやジャストシステム社の一太郎をはじめ、ワードプロセッサでHTMLをサポートするものが増えているほか、Windows用にMicrosoft社のFrontPage、マッキントッシュ用にAdobe社のPagemillなど、様々なHTML専用のデザイン・ツールも出回っており、これらを利用すればユーザーはHTMLの機能を特に知る必要がなく、非常に便利です。もちろん、それらを使わず記述することはできます。
ワードプロセッサのHTML機能やHTML専用のデザイン・ツールを使うと、どうしても不必要なタグが入ったりするため、場合によってはファイルサイズが倍ぐらいまで脹らんでしまいます。また、仕上がったHTML文書は、大文字小文字の使い方や細かいところへプログラマーの性格が反映されることは避けられません。結局、筆者の場合、いろいろ試しつつも、未だにWindowsの「メモ帳」が唯一の記述道具という実状です。
HTMLの記述
専用ツールを使わずHTMLを記述するには、まずテキストエディタとブラウザ(閲覧ソフト)を用意する必要があります。テキストエディタで文書を作成し、ブラウザでその結果を確認しながら進めてゆくわけです。ブラウザには文書の再ロード(Reload)機能があるので、更新したら時々ブラウザを再ロードし、文書の結果をチェックします。なお、これらの文書は、それがHTML文書であることをブラウザに判断させるため、「.html」という拡張子を付けて保存しなくてはなりません(MS-DOSだと「.htm」)。
HTMLに日本語を使う場合、漢字コードが問題となります。ブラウザによっては、表示コードを制限される場合もありますが、インターネット内で最も一般的に使用されるのは、電子メールで使う7ビットJISコードです。
漢字コードの種類
| 漢字コード | 特徴 |
|---|
| ISO-2022-JP (7ビットJIS) |
最も一般的 |
|---|
| EUC-JP |
UNIX系に多い |
|---|
| シフトJIS |
パソコンで用いられる |
|---|
|
その他、WYSIWYGエディタを使ったり、他の文書形式(LaTeXやワードプロセッサ)から変換したりすることができます。
ブラウザについて
ブラウザというのは文字通りBrowse(拾い読み)をする道具であり、Windowsのエクスプローラもブラウザの一種です。そして、WWWの世界に限定した場合、大きく分けてネットスケープやインターネット・エクスプローラ(Microsoft社)といったソフト・グループと、それらのソフト上でネットサーフィンをするためのグループの2つに分けられます。このマニュアルでブラウザという場合、特に注をつけない限り前者を指し、上記以外では現在のWWWブームの原点ともいえるモザイクが有名です。また、比較的新しい製品ではGrailやOracleといったブラウザがあります。
後者は、大学のプロジェクトとして始められ、その後、企業化されたヤフーに代表される検索エンジンの類や、バーチャル・ツーリストといった世界地図でブラウズ(検索)するものから、CNNのWWW版といわれるポイントキャスト・ネットワークまで多様です。ただ、ハイパーテキストの記述がテーマなので、これ以上こちらのグループへは触れません。
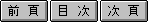
![]()